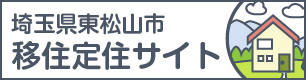本文
居住費・食費の負担減額を受けるには
特定入所者介護(予防)サービス費
施設入所サービスやショートステイサービスを利用したときには、施設サービス費用の利用者負担割合に応じた額に加えて、原則として居住費・食費・日常生活費が全額自己負担となりますが、低所得者については、所得金額等に応じて居住費・食費の自己負担の限度額が設けられており、限度額を超えた分は「特定入所者介護(予防)サービス費」として、介護保険から給付され、負担軽減を受けることができます。
なお、負担の軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定」の申請が必要となります。また、毎年7月が更新月となっており、更新手続きが必要になります。
対象となるサービス
- 介護保険施設[介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院]における居住費と食費
- 地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)における居住費と食費
- 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護における居住費と食費
- 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護における居住費と食費
(注釈)通所系サービス(デイサービス等)での食費は対象となりません。
認定を受けるための要件
所得要件
本人及びその同一世帯構成員(本人の配偶者については、別世帯の場合も含む)が市民税非課税であること。
資産要件
本人に配偶者がいない場合には本人名義の預貯金等の金融資産が負担段階に応じた金額を超えていないこと。
| 負担段階 | 課税年金収入額、非課税年金収入額及び その他の合計所得金額の合計 |
金融資産 |
|---|---|---|
| 第1段階 |
(生活保護受給者) |
- |
| 第2段階 | 80万9,000円以下の方 | 650万円 |
| 第3段階1 | 80万9,000円超、120万円以下の方 | 550万円 |
| 第3段階2 | 120万円を超える方 | 500万円 |
本人に配偶者(別世帯・内縁関係の場合を含む)がいる場合には本人と配偶者名義の預貯金等の金融資産が負担段階に応じた金額超えていないこと。
| 負担段階 | 課税年金収入額、非課税年金収入額及び その他の合計所得金額の合計 |
金融資産 |
|---|---|---|
| 第1段階 | (生活保護受給者) | - |
| 第2段階 | 80万9,000円以下の方 | 1650万円 |
| 第3段階1 | 80万9,000円超、120万円以下の方 | 1550万円 |
| 第3段階2 | 120万円を超える方 | 1500万円 |
補足事項
- 上記金融資産には、株式などの有価証券、現金、時価評価額を容易に把握できる金銀などを含みます。生命保険、時価評価額の把握が困難な宝石や自動車などの動産や土地建物などの不動産は含みません。
- 借入金や住宅ローンなどの負債がある場合には、預貯金等の合計金額から差し引きます。
- 生活保護受給者については、各要件を満たしていない場合でも認定の対象となります。
負担限度額認定フローチャート [PDFファイル/245KB]
利用者負担段階ごとの負担額
所得要件・資産要件の両方を満たしている場合、本人の所得金額や生活保護の受給の有無などに応じて、下記の利用者負担段階の「第1段階」から「第3段階2」のいずれに該当するか判定します。
なお、平成28年8月からは、遺族年金や障害年金などの非課税年金の受給額も利用者負担段階の判定にあたっての算定対象となります。
第1段階
対象者
- 生活保護受給者
- 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
1日あたりの居住費・食費の目安
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 880円 | 550円 | 550円 (注釈1) |
0円 |
300円 |
(注釈1)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、380円
第2段階
対象者
- 住民税が世帯非課税で、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金額の合計が80万9,000円以下の方
- 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
1日あたりの居住費・食費の目安
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 880円 | 550円 | 550円 (注釈2) |
430円 | 390円 (注釈3) |
(注釈2)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、480円
(注釈3)短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用した場合には、600円
第3段階1
対象者
- 住民税が世帯非課税で、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金額の合計が80万9,000円超、120万円以下の方
- 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
1日あたりの居住費・食費の目安
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (注釈4) |
430円 | 650円 (注釈5) |
(注釈4)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、880円
(注釈5)短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用した場合には、1,000円
第3段階2
対象者
- 住民税が世帯非課税で、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金額の合計が120万円を超える方
- 境界層に該当する方(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる方)
- 「所得要件」を満たさないため、当該認定の対象にならない場合で、「特例減額措置」を受けられる方(特例減額措置については、このページの下部をご覧ください)
1日あたりの居住費・食費(基準費用額)の目安
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (注釈6) |
430円 |
1,360円 |
(注釈6)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、880円
(注釈7)短期入所生活介護又は短期入所療養介護を利用した場合には、1,300円
第4段階
対象者
利用者負担第1段階から第3段階2に該当しない方
1日あたりの居住費・食費(基準費用額)の目安
| ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (注釈8) |
437円 (注釈9) |
1,445円 |
(注釈8)介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、1,231円
(注釈9)室料を徴収する一部の介護老人保健施設・介護医療院を利用した場合には、697円
また、介護老人福祉施設又は短期入所生活介護を利用した場合には、915円
申請手続き
必要な提出書類
必ず提出する必要がある資料
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 収入等に関する申告書
- 同意書
- 預貯金通帳等の写し(本人及び配偶者名義のもの)
金融機関名、支店、口座番号、名義人名等がわかるページの写し
直近2か月以内の取引内容がわかるページの写し
(補足)生活保護受給者については、申請書への記入押印で足り、同意書及び預貯金通帳等の写しの提出は不要です。
以下は保有している場合に提出する必要がある資料(本人及び配偶者名義のもの)
- 定期預金を保有している場合には、定期預金通帳・証書や残高証明書の写し
- 有価証券を保有している場合には、取引残高報告書や保有資産残高証明書の写し
- 負債(借入金や住宅ローンなど)がある場合には、借用証書の写しや借入残高証明書の写し
申請書等は下記のページからダウンロードしてください。
注意事項
- 上記の提出書類に不備がある場合や添付資料の提出を拒否する場合には、認定を受けることができません。
- 同意書に基づき、適正な申告がなされているかどうか金融機関に照会する場合があります。
- 申請にあたり、虚偽の申告をするなどして、不正に特定入所者介護サービス費を受給していたことが判明した場合には、不正に受給した額の返還を求め、また、特に悪質性が高いと認められる場合には、不正に受給した額の最大2倍の加算金の支払いを求めることがあります。
個人情報に関する取扱い
提出していただいた書類及び金融機関への照会に関する同意書につきましては、個人情報保護の観点から適正に取扱い、介護保険負担限度額認定の審査判定の目的の範囲内でのみ利用し、適切に管理いたします。
特例減額措置とは?
高齢夫婦世帯(年齢要件はありません)などでその一方が施設に入所し、施設入所に伴う利用料等の負担により在宅で生活するもう一方の配偶者の生計が困難となるような場合に、下記の要件を満たし、認定を受けた方は「特例減額措置」を受けることができます。なお、特例減額措置については、施設に入所する場合のみが対象となり、ショートステイサービス(短期入所)は対象になりません。
適用要件
- 本人を含む世帯の構成員(施設入所に伴う住所変更などにより世帯が別になっている場合は同一世帯とみなします。以下、同義。)が2人以上であること
- 本人又はその世帯構成員(別世帯の配偶者・内縁関係の配偶者を含む)に住民税が課税されていることにより、上記の所得要件を満たさないこと
- 本人世帯(別世帯配偶者を含む。以下、同義)の年間収入(注釈10)から、施設入所に伴う利用者負担額(注釈11)を除いた額が80万9,000円以下であること
- 本人世帯の預貯金等(現金・有価証券等含む)の額が450万円以下であること
- 世帯が日常生活に供する家屋や土地その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産が有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
(注釈10)「年間収入」は、サービスを受ける日の属する年の前年(その属する日が1月から7月までの場合は前々年)の公的年金等収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。なお、平成28年8月1日以降は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、特別控除金額を合計所得金額から控除します。)を合計した金額です。
(注釈11)「利用者負担額」は、介護サービス費用の自己負担額と、利用者負担第4段階の場合の居住費・食費の利用者負担額を合計した金額です。
申請手続きや詳細につきましては、下記までお問い合わせください。