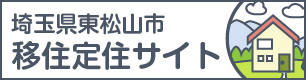本文
郷土の児童文学「天の園」の世界
東松山市が舞台「天の園」
打木村治の作品「天の園」は、明治後半から大正時代、作者が小学校時代を過ごした唐子村(現在の唐子地区)を舞台に描かれた全六部の長編小説で、「路傍の石」「次郎物語」とともに三大児童文学と言われています。


小説の主人公は、小学校時代の作者がモデルの「河北 保」。保少年の小学校六年間の成長の過程が学年ごとに一冊ずつ収められています。
小説には、都幾川や農村の豊かな自然の中で、伸びやかに遊ぶ子どもたちや、子どもたちの成長をやさしく見守る大人たちがたくさん登場し、地域の人々との交流を通して心豊かにたくましく成長していく子どもたちの様子が情緒豊かに描かれています。

豊かな自然

「村にあんなきれいな川があって、ほんとにしあわせだと先生は思う。…・東京に親類の子がいたら、おみやげに都幾川の石をもっていってやるといい…・この唐子村の自然をもっていってやんなさい。子どもには、自然が一等の先生なんだから」天の園第四部(偕成社)より
病身の夫と5人の子どもを抱えて唐子に帰ってきた母かつらは、「景色だけではメシは食えんぞ」という兄に、「景色でおなかのくちくなるような子に育てます」と答えたのでした。天の園第四部(偕成社)より

「天の園」記念碑は唐子中央公園にあります。
地域コミュニティー

小説の中にしばしば登場する村の鎮守お諏訪さまの祭り。村人が一堂に会するこうした行事は、人々の大切なコミュニケーションの場にもなっていました。現在でも7月下旬に、獅子舞奉納(ササラ獅子舞)が行われています