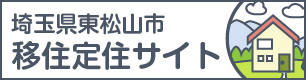本文
生後2か月から行う予防接種
ロタウイルス
令和2年10月1日より、ロタウイルスワクチンが定期予防接種となります。令和2年8月1日以降に生まれた方が対象となります。ただし、定期接種(公費対象)は令和2年10月1日以降に接種したものが対象となります。令和2年9月30日以前に接種した場合は、任意接種の扱いとなり公費対象となりませんのでご注意ください。
ロタウイルスワクチンには1価生ワクチン(ロタリックス)と5価生ワクチン(ロタテック)の2種類がありますが、どちらもロタウイルス胃腸炎に対して同様の予防効果が見込まれています。なお、実施にあたってはそれぞれのワクチンで接種回数や接種量が異なるため、原則として同一製剤により接種を完了する必要があります。
対象者
令和2年8月1日以降に生まれた方で、次の1.又は2.に該当する方
- 生後6週から生後24週までの間にある者(1価ロタウイルスワクチンを接種する場合)
- 生後6週から生後32週までの間にある者(5価ロタウイルスワクチンを接種する場合)
ワクチン
1価ロタウイルスワクチンと5価ロタウイルスワクチンの2種類のうちいずれかを接種
方法
個別予防接種
ロタワクチン取り扱い医療機関(市内) [PDFファイル/86KB]
注意
- この予防接種は原則、同じワクチンで接種する必要があります。
- どちらのワクチンも同様の予防効果があります。
接種時期
生後6週から生後24週または、生後32週まで(接種するワクチンによって、接種時期が異なります。)
注意
予診票の欄外にある接種時期をご確認ください。これを過ぎると定期予防接種として接種できません。
接種回数と接種間隔
1価ロタウイルスワクチン(ロタリックス)の場合
<回数>27日以上あけて2回。
<1回目の接種期間>生後6週0日後(標準的には生後2か月)から14週6日後までに接種することが推奨されています)
(注意)余った予診票(3回目)は破棄してください。
5価ロタウイルスワクチン(ロタテック)の場合
<回数>それぞれ27日以上あけて3回
<1回目の接種期間>生後6週0日後(標準的には生後2か月)から14週6日後までに接種することが推奨されています。)
以下の状態の場合には、予防接種を受けることができません
- 明らかな発熱を呈している方(37.5℃以上)
- 重篤な急性疾患に罹っていることが明らかな方
- このワクチンの成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方
- ロタウイルスワクチンを接種してから27日以上の間隔をおいていない方
- 1価ワクチン(ロタリックス)を接種する場合は生後24週1日、5価ワクチン(ロタテック)を接種する場合は生後32週1日に到達している方
- 以前に、この予防接種に相当する予防接種をした方で、この予防接種を受ける必要がないと認められる方
- 腸重積症の既往歴があることが明らかな方、先天性消化管障害を有する方(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる方
- その他、予防接種を行うことが不適当であると医師が判断した方
予防接種を受けるにあたって注意を要する方(接種前に医師とよく相談してください)
次のいずれかに該当する方は、接種する前に医師と充分に相談してください。その病気を診てもらっているかかりつけ医がいる場合、予防接種をする医師と別のときは、必ず、そのかかりつけ医にこの予防接種をして良いか確認してください。
- 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する方
- 予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある方
- 過去にけいれんの既往のある方
- 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全の方がいる方
- このワクチンの成分に対してアレルギーを呈するおそれのある方
- 活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害のある方
接種後の注意点
- 急な副反応が生じることがありますので、接種後30分程度は医療機関に留まるようにしてください。
- 接種当日は安静を保って激しい運動は控えてください。
- 接種当日の入浴は差し支えありません。
- 予防接種後28日間は緊急性のない場合、抜歯、扁桃腺手術、ヘルニア手術等は避けてください。
- 接種後約1週間(生ワクチンを同時接種した場合は約4週間)は副反応の出現に注意してください。また、接種後約2週間は特に腸重積症状の出現に注意してください。
- 接種後、体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
腸重積症について
- 腸重積症は、腸の一部が隣接する腸管に入り込み、腸が閉塞した状態になる緊急性の高い病気で、速やかな治療が必要です。
- ワクチンの接種にかかわらず、生後3か月~2歳くらいまでの赤ちゃんがかかりやすい病気です。
- ロタウイルスワクチンの接種(特に初回接種)後、1~2週間程度の間は、腸重積症の発症リスクが高まるとの報告があります。
腸重積症を発症した場合、発症から時間が経過するほど、外科手術になる可能性が高まるため、接種回数にかかわらず、接種後1~2週間程度の間に、次のような症状が1つでも見られたときは、腸重積症が疑われるため、速やかに医師の診察を受けてください。
- 嘔吐を繰り返す
- 泣いたり不機嫌になったりを繰り返す
- 血便が出る
- ぐったりして、元気がない
ロタウイルス胃腸炎
ロタウイルスによる胃腸炎は、短時間で嘔吐と急激な水溶性の下痢便を頻回に排泄することが主症状とし発熱が3割~5割程度見られます。脱水を起こしやすく、乳幼児の場合、特に注意が必要です。通常は3~4日程度で軽快しますが、脱水の程度によって、経口補液・点滴での輸液を必要とすることもあります。
国内でのロタウイルス胃腸炎は毎年3~5月に流行し、生後6か月~2歳までにかかることが多く、5歳までにほとんどの子どもがかかります。潜伏期間は24~48時間で、乳幼児期では約40人に1人の割合で重くなり、けいれん、腎不全、脳症などの合併症のため入院治療する場合があります。ワクチン導入前は5歳未満の急性胃腸炎の半数程度がロタウイルスが原因とされてきました。
日本では「G1」「G2」「G3」「G4」「G9」という5つの型が多く見られ、どの型がはやるのか、年によって違うといわれています。ロタウイルスは一度感染しても別の型で感染を繰り返す可能性があります。
ロタウイルスワクチンの効果
ロタウイルスのワクチンには、ロタリックス(1価ワクチン 2回接種)とロタテック(5価ワクチン 3回接種)の2種類があります。いずれのワクチンも、「G1」「G2」「G3」「G4」「G9」の5つの型に対する予防効果が示唆されています。
ロタウイルスワクチンの違いと比較
ロタウイルスワクチンの違いと比較[PDFファイル/78KB]
ロタウイルスワクチンの定期接種に関するQ&A
5種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ)ワクチン
・五種混合ワクチンの接種回数・接種間隔は「四種混合ワクチン」と同じです。
・原則として同一のワクチンで接種を行う為、初めて接種を開始する方は、五種混合ワクチンで開始します。
・「四種混合+ヒブ」で接種を開始している方に対しては「四種混合+ヒブ」ワクチンで接種します。
方法
対象
生後2か月から7歳6か月未満
原則、5種混合で初回接種を始めた方(4種混合(3種混合)、ヒブ、不活化ポリオを接種していない方)
接種間隔と回数
<初回接種> 20日から56日までの間隔をおいて3回
<追加接種> 初回接種終了後1年以上の間隔をおいて1回
(3回目終了後12か月から18か月の間が望ましい)
5種混合ワクチン(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、不活化ポリオ)ワクチン
【お知らせ】 「四種混合ワクチン」の販売終了に伴う取り扱いの変更について
「五種混合ワクチン」の発売に伴い、「四種混合ワクチン」は在庫の出荷をもって販売終了となりました。
「四種混合ワクチン」の販売中止に伴い同一ワクチンで定期接種が完了できない場合は、既に接種されたインフルエンザ菌b型(ヒブ)ワクチンの回数によらず、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了するこが可能です。
四種混合から五種混合に切り替えて接種する際の注意点と予診票の取り扱いについて
<保護者様へ>
四種混合から五種混合に切り替えて接種する際、後から接種する五種混合ワクチンから見て、直前の四種混合ワクチンとの接種間隔が添付文書に定められたものとなるよう、必要な日数を確保する必要があるますので、予約の際に医療機関にご確認ください。
また、予診票については、使用するワクチンの予診票を使用することになっておりますので、事前に、希望するワクチンと予診票が合っているか確認してください。
なお、予診票をご希望の場合は、母子手帳と医療機関名の分かるものを準備して健康推進課(保健センター)へお越しください。
<医療機関の方へ>
万が一、接種当日に異なった予診票をお持ちの方がいた場合には、医療機関が接種可能かの判断をしていただき、可能な場合は、予診票のワクチン名を訂正してご使用ください。
方法
対象
生後2か月から7歳6か月未満
「四種混合+ヒブ」で接種を開始している方に対しては「四種混合+ヒブ」ワクチンで接種します。
「四種混合ワクチン『クアトロバック』」の販売終了に伴い、同一のワクチンで接種完了できない場合は医師にご相談ください。
接種間隔と回数
<初回接種> 20日から56日までの間隔をおいて3回
<追加接種> 初回接種終了後1年以上の間隔をおいて1回
(3回目終了後12か月から18か月の間が望ましい)
5種混合ワクチン(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
インフルエンザ菌b型(ヒブ)
方法
対象
2か月から5歳未満
「四種混合+ヒブ」で接種を開始している方に対しては「四種混合+ヒブ」ワクチンで接種します。
接種回数と接種間隔
年齢により接種回数が異なります。
2か月から7か月未満で接種を始めた方
<初回>4週間(医師が必要と認めるときは3週間)以上、標準的には8週間までの間隔で3回(1歳未満)
<追加>初回3回目終了後7か月以上、標準的には13か月までの間で1回
(注意)ただし、初回2回目及び3回目の接種は、1歳を超えた場合は接種せず、初回の最後の接種が終了後、4週間(医師が必要と認めるときは3週間)以上の間隔で追加接種を1回行うこと。
7か月から1歳未満で接種を始めた方
<初回>4週間(医師が必要と認めるときは3週間)以上、標準的には8週間までの間隔で2回(1歳未満)
<追加>初回の2回目終了後7か月以上、標準的には13か月までの間隔で1回
(注意)ただし、初回2回目の接種は、1歳を超えた場合は接種せず、初回1回目の注射終了後、4週間(医師が必要と認めるときは3週間)以上の間隔で追加接種を1回行うこと。
1歳~5歳未満で接種を始めた方
1回
インフルエンザ菌b型(ヒブ)とワクチンについて
ヒブは、正式にはヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌で、細菌による子どもの感染症の主な原因菌の一つです。名前は似ていますが、主に冬に流行するインフルエンザのウイルスとはまったく別のものです。
せきやくしゃみなどにより感染し、そのほとんどは症状を起こすことはありませんが、一部の人で菌が血液中に入り込み、髄膜炎や肺炎などの全身感染症や、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などを起こします。全国で年間600人くらいの子どもがヒブ髄膜炎にかかっており、約5パーセントが死亡し、約25パーセントに発育障害や聴力障害、てんかんなどの後遺症が残ります。
3か月から5歳未満(特に2歳未満)にかかりやすいので注意が必要です。
このワクチンを4回接種した人のほぼ100パーセントに抗体(免疫)ができ、ヒブ感染症に対する高い予防効果が認められています。
ワクチンの製造にウシの由来成分が使用されていますが、このワクチン接種が原因でTSE(伝達性海綿状脳症)にかかったという報告はありません。
発病のピークは8か月頃のため、6か月までに接種することをお勧めします。
副反応について
- 局所反応 発赤、腫れ、しこり、疼痛
- 全身反応 発熱、不機嫌、異常号泣、食欲不振、嘔吐、下痢、不眠、傾眠等
- 重い副反応 海外で非常にまれにショック・アナフィラキシー様症状(じんましん・呼吸困難等)けいれん(熱性けいれん含む)血小板減少性紫斑病が報告されています。
小児肺炎球菌
小児肺炎球菌ワクチン変更のお知らせ
「13価小児用肺炎球菌ワクチン」に加えて、令和6年4月1日から「15小児用肺炎球菌ワクチン」が定期接種になりましたが、令和6年10月1日から新たに「20価小児用肺炎球菌ワクチン」が定期接種に追加されます。それに伴い「13価小児肺炎球菌ワクチン」は販売中止のため定期接種できなくなります。
令和6年10月1日以降に、初めて接種する方に使用する小児用肺炎球菌ワクチンは、「20価小児用肺炎球菌ワクチン」が基本となります。
過去に「13価小児用肺炎球菌ワクチン」を受けていた方が「20価小児用肺炎球菌ワクチン」の交互接種は可能です。
「15価小児用肺炎球菌ワクチン」を受けた方が「20価小児用肺炎球菌ワクチン」の交互接種はできませんので、同一のワクチン接種で完了します。
「15価小児用肺炎球菌ワクチン」と「20価小児用肺炎球菌ワクチン」の効果に大きな差はないとされています。
方法
対象
2か月から5歳未満
接種回数と接種間隔
接種開始年齢により接種回数が異なります。
2か月から7か月未満で接種を始めた方
<初回>1歳までに4週間以上の間隔で3回
<追加>初回3回目終了後60日以上の間隔で、1歳以降1回(標準的な接種期間は1歳から1歳3か月)
(注意)
- 初回2回目及び3回目の接種は2歳を超えた場合は行わないこと。
(追加接種は実施可能)。 - 初回2回目の接種が1歳を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと(追加接種は実施可能)。
7か月から1歳未満で接種を始めた方
<初回>標準的には1歳1か月までに4週間以上の間隔で2回
<追加>初回終了後60日以上の間隔で、1歳以降に1回
(注意)ただし、初回2回目の接種は、2歳を超えた場合は行わない(追加接種は実施可能)。
1歳から2歳未満で接種を始めた方
60日以上の間隔をおいて2回
2歳から5歳未満で接種を始めた方
1回
小児肺炎球菌とワクチンについて
肺炎球菌は、細菌による子どもの感染症の主な原因菌の一つです。
咳やくしゃみなどにより感染し、多くの子どもがのどや鼻に保菌します。体力や抵抗力が落ちた時などに、菌が体内に入り込んで、年間200人くらいが細菌性髄膜炎を発症し、その他に菌血症、肺炎、副鼻腔炎、中耳炎といった病気を引き起こすことがあります。
肺炎球菌性の髄膜炎になった人のうち、約40パーセントの子どもが水頭症、難聴、発育障害などの後遺症が残ったり死亡したりしています。
3か月から5歳未満にかかりやすいので注意が必要です。
約90種類ある肺炎球菌のなかでも、子どもの肺炎球菌を起こしやすい15種類(15価)と20種類(20価)の血清型に対応して作られています。
ワクチンの効果
子どもで重症になりやすい15種類(15価)と20種類(20価)の血清型に対して、肺炎球菌による侵襲性感染症の予防(細菌性髄膜炎など)を予防するように作られたワクチンです。
副反応について
| 10%以上 | 1~10%未満 | 1%未満 | |
|---|---|---|---|
| 代謝及び栄養障害 | 食欲減退 | ||
| 精神障害 | 易刺激性(56.4%) | ||
| 神経系障害 | 傾眠 | ||
| 一般・全身障害 | 発熱(55.6%) | 蕁麻疹 | |
| 投与部位の状態 |
紅斑(66.2%) 硬結(60.9%) 腫脹(50.9%) 疼痛(55.6%) |
注射部位蕁麻疹 |
厚生労働省Q&Aより抜粋
| 10%以上 | 1~10%未満 | 1%未満 | |
|---|---|---|---|
| 代謝及び栄養障害 | 食欲減退 | 下痢、嘔吐 | |
| 精神障害 |
易刺激性(79.3%) 傾眠状態(78.5%) |
||
| 神経系障害 |
筋緊張低下 不安定睡眠 |
||
| 一般・全身障害 | 発熱(39.4%) | 発疹、紫斑、アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、蕁麻疹、顔面浮腫、呼吸困難、気管支痙攣 | |
| 投与部位の状態 |
紅斑(57.3%) 硬結(60.9%) 腫脹(45.1%) 疼痛(59.9%) |
硬結 注射部位過敏反応 |
(添付書類より抜粋)
| 重い副反応 | 備考 |
|---|---|
| 非常にまれにショック・アナフィラキシー様症状(備考参照)痙攣(熱性痙攣含む)血小板減少性紫斑病が報告されています。 | (参照)「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。呼吸困難、全身にひどいじんましんが出るほか、吐気、嘔吐(おうと)、血圧低下等、ショック状態になるような激しい全身反応のことです。 |
(添付文書より抜粋)
リンク
小児用肺炎球菌ワクチンの変更に関するQ&A(厚生労働省)<外部リンク>
B型肝炎
接種方法
対象者
1歳未満
HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児の取扱い
母子感染予防を目的とした予防接種は健康保険が適用となるため「健康保険によりワクチンを1回でも接種した方」は定期予防接種の対象とはなりません。
接種回数
3回
接種間隔
- 4週間以上の間隔で2 回
- 更に、1回目の接種から20週間以上の間隔で1回
標準的な接種スケジュール
(1回目) 2か月
(2回目) 3か月(1回目の1か月後)
(3回目) 7か月から8か月(1回目の5か月から6か月後)
B型肝炎について
B型肝炎の感染者は、日本国内で約100万人と推定されています。
B型肝炎に感染すると、急性肝炎から劇症肝炎を起こし死に至るケースや、「キャリア(持続感染:ウイルスを体内に保有した状態)」となり、慢性肝炎、肝硬変、肝臓がんへと進行する危険性が高くなってしまいます。
B型肝炎は、「血液」「唾液」「汗」「体液(精液)」を介して感染します。
常識的な社会生活を心がけていれば、日常生活の場では、B型肝炎に感染することはほとんどないと考えられていますが、キャリアの母親や家族、保育所などでキャリアの児から、その他成長してからは性行為など、感染する機会は、生涯を通じて潜んでいます。
B型肝炎ワクチンについて
「ヘプタバックス」と「ビームゲン」の2種類のワクチンがあります。抗体獲得率に差はほとんどありませんので、医療機関で接種できる方を接種してください。
特に、低年齢の子どもがB型肝炎に感染すると、「キャリア」になりやすいといわれています。ワクチンは生後すぐから受けられますが、通常は2か月から接種を始めるのがおすすめです。
なお、母親がB型肝炎キャリアであることがわかった場合は、子どもへの感染を防ぐため、出生時に、健康保険でB型肝炎の予防接種を行っています。健康保険でB型肝炎の予防接種を1回でも受けた方は、定期予防接種の対象ではありません。
副反応について
|
|
ヘプタバックス |
ビームゲン |
|---|---|---|
|
防腐剤(チメロサール)の含有 |
無 |
有 |
|
ゴム栓 |
乾燥天然ゴム(ラテックス) (注意)ラテックス、バナナ、キウイ、栗、アボガドなどのアレルギーがある場合は、医師にご相談ください。 |
合成ゴム |
|
重篤な副反応 (0.1パーセント未満) |
ショック、アナフィラキシー、多発性硬化症、散在性脳脊髄炎、ギランバレ症候群、脊髄炎、視神経炎、末梢神経障害 |
ショック、アナフィラキシー、多発性硬化症、散在性脳脊髄炎、ギランバレ症候群 |
|
その他 (5パーセント未満)
|
発熱、局所症状(疼痛、発赤、硬結、掻痒感、熱感、腫脹)、頭痛、全身倦怠感消化器症状(嘔吐、腹痛、下痢、食欲不振)関節痛、筋肉痛、手の脱力、蕁麻疹 |
発熱、発疹、局所症状(疼痛、発赤、硬結、掻痒感、熱感、腫脹)、頭痛、全身倦怠感、消化器症状(嘔吐、腹痛、下痢、食欲不振)、関節痛、筋肉痛 |
【厚生労働省】HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談
「感染症・予防接種相談窓口」では、子宮頸がん(HPV)ワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。
(注意)行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
(注意)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。
(注意)オペレーターへの暴言、性的発言、セクハラ等の入電はご遠慮ください。他の入電者様の対応に支障が生じております。
詳細は 感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。
予防接種による健康被害救済に関する相談
東松山市健康推進課(保健センター)予防接種担当にご相談ください。
HPVワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度については、『予防接種健康被害救済制度』のページをご覧ください。
『予防接種健康被害救済制度』(厚生労働省)<外部リンク>