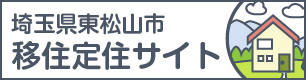本文
地域での助け合い(自主防災組織)
阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋から地域住民の手によって多くの人が助け出されました。また、火災発生に対して数多くの市民が消火活動を行い、延焼拡大を阻止しました。
自主防災組織の結成
災害時には、防災機関の活動を待つだけでなく、地域の人々が協力して、初期消火、被災者の救出・救護、避難誘導、避難所の運営等を行えば、被害をより小さくすることができます。
自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る」という連帯感に基づき、災害時における地域の防災活動を円滑に行うとともに、日頃から災害に備えた準備を行うため、地域の人々が自発的に結成する組織です。
通常、町内会や自治会単位に結成され、「〇〇自治会自主防災会」といった名称の団体が多いようです。その規模は、住民が協力して自分たちの地域を守るという連帯感が保持される程度の世帯数で組織されるのが望ましいといわれています。
市では、自治会等を単位とした自主防災組織の結成及び活動の支援を推進しています。
災害に強いまちづくりを行うため、自主防災組織の活動に積極的に参加しましょう。
自主防災組織の結成手順
- 地震などの災害が発生した状況や過去の被害履歴について調べ、自主防災活動の重要性を確認します。
- 町内会や自治会の役員会等で、自主防災組織の結成について、話し合います。
- 市の担当職員に災害が発生したときの状況や他の組織の活動状況等について説明してもらうと、結成の合意が得られやすいでしょう。
- 町内会や自治会の総会で、自主防災組織の結成(未定稿)を議題とし、討議・可決します。
- 規約、防災計画などを総会で議決します。
- 市に自主防災組織の設立を報告します。
- 自主防災組織の活動を開始します。
自主防災組織の構成
町内会や自治会などの代表者、役員が自主防災組織の代表者、役員を兼ねるような組織が望ましいです。
自主防災組織の結成に当たって、気をつけておきたいポイント
- 政治色や宗教色を出さない
- 無理のない防災計画を
- 多くの人が楽しく参加できるように
自主防災組織の活動と心構え
災害から住民の生命、身体及び財産を保護するためには、市など防災機関が総力をあげて対策を講ずるとともに、住民一人ひとりが十分な防災意識を持ち、防災訓練を積み重ねるなど、防災対策を地域で実践しなければなりません。
平常時
- 防災知識の習得
- 危険箇所の把握
- 防災計画の作成
- 世帯台帳の作成
- 防災用資機材の整備
- 自主防災訓練の実施
- 防災訓練への参加
- 応急救命講習の受講
- 地域内の他組織との連携
災害時
- 出火防止及び初期消火
- 地域における相互扶助による安否の確認及び被災者の救出活動
- 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護
- 自力による生活手段の確保